自己肯定感を高める7つの習慣と実践法【初心者向け】
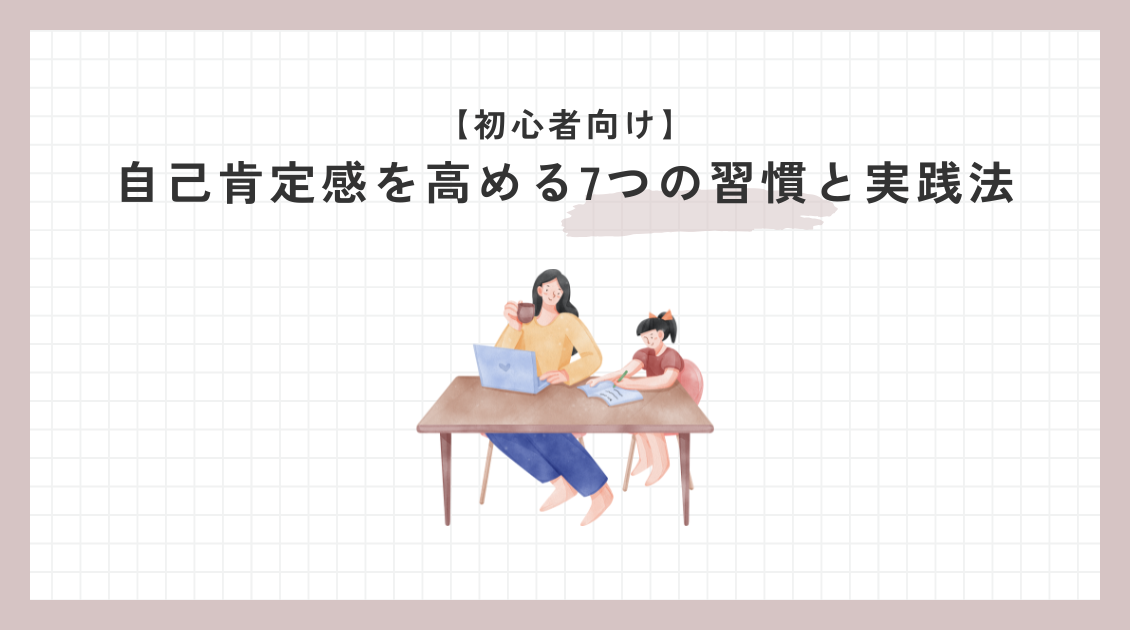
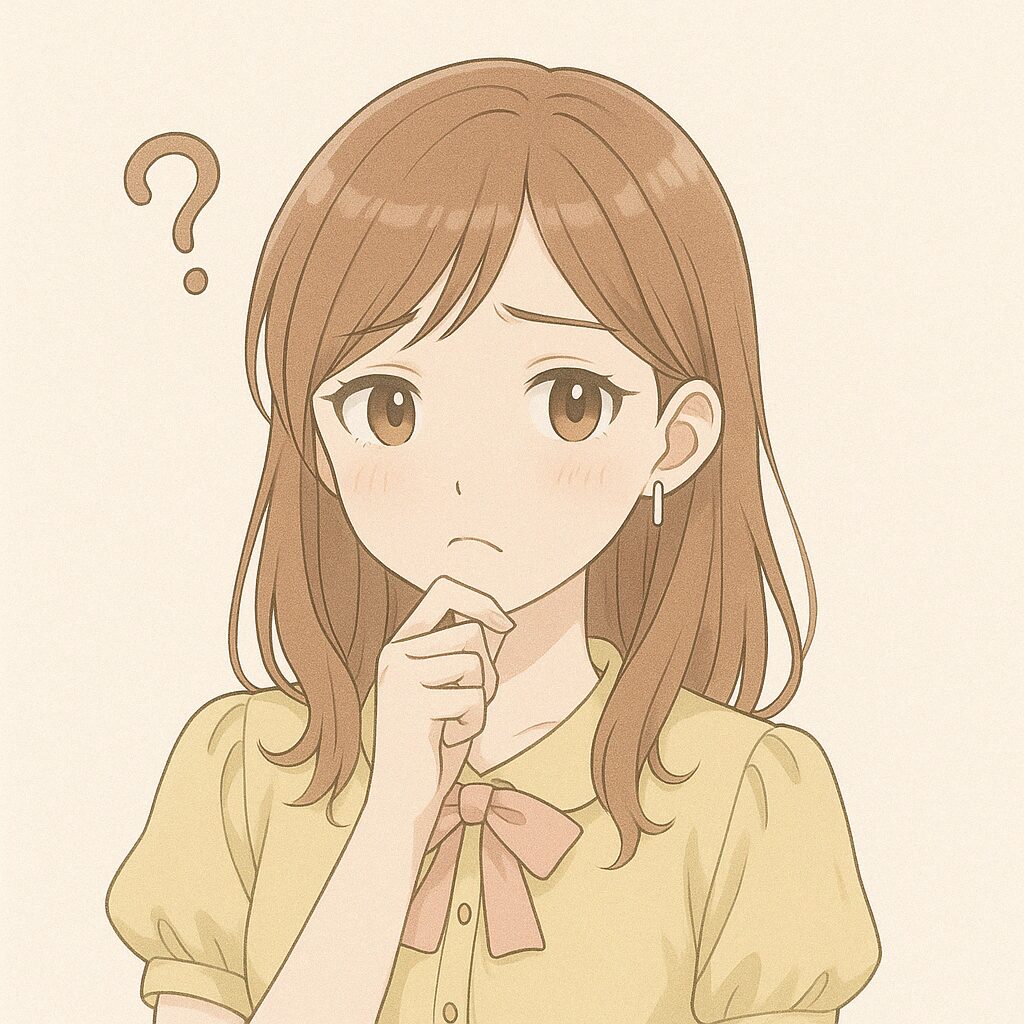
「なんで私って、こんなに自信がないんだろう…」
「人と比べてばっかりで、疲れる…」

大丈夫。そんなふうに感じているのはあなただけじゃありません🥺
実際に私も、同じように思っていて苦しんだ時期がありました。
この記事では、自己肯定感を高めたいと考えている方に向けて、
- 自己肯定感が低いことで起こる問題
- 自己肯定感を高めるための具体的な方法
- 習慣化するためのコツ
- おすすめの本
などを、わかりやすく・実践しやすく紹介していきます。
読んだあとに、「少しだけ自分に優しくなれる」方法をたくさんお伝えしていくのでぜひ参考にしてくださいね。
自己肯定感とは何か?
「自己肯定感」という言葉、最近よく耳にしませんか?
自己肯定感とは、「ありのままの自分を受け入れ、自分には価値があると感じられる感覚」のことを指します。
これは「自分が優れている」と思い込むことではなく、
たとえ失敗しても、うまくいかないことがあっても、「それでも自分は大丈夫」「自分には存在価値がある」と思える力のことです。
なぜ自己肯定感が重要なのか?
自己肯定感が高い人と低い人には、それぞれ次のような傾向があります。
| 自己肯定感が高い人 | 自己肯定感が低い人 |
|---|---|
| 失敗してもすぐに立ち直れる 他人と比べずに自分のペースを大切にできる 人間関係で無理をしすぎない 自分の意見を持ち、発言できる | 些細なことで自分を責めてしまう 人と比べて落ち込む 他人に合わせすぎて疲れる 自分には価値がないと思い込んでしまう |
つまり、自己肯定感は、人生の土台とも言える大切な感覚なんです。
日本人が自己肯定感を持ちにくい理由
文部科学省が実施した「子供の生活と意識に関する調査」では、
「自分自身に満足している」と答えた日本の中学生はたったの約30%。
これは、他の先進国と比べてもかなり低い水準です。
この背景には、以下のような日本社会特有の価値観が影響していると考えられます。
- 「謙虚が美徳」という文化
- 集団の中で目立たないことが良しとされる
- 失敗を許容しにくい空気
- 過度な「空気を読む」プレッシャー
これらが、「自分らしくいること」「自分を認めること」を難しくしている要因になっているのです。
自己肯定感が低いとどうなる?
自己肯定感が低いと、自分に対する信頼感が持てなくなり、
日常生活のあらゆる場面で「生きづらさ」を感じやすくなります。
ここでは、自己肯定感が低いことによって起きる具体的な問題を、
3つの側面から見ていきましょう。
日常生活への影響
「どうせ自分なんて」と思いやすくなる
何か新しいことに挑戦する前から、「自分には無理」「やっても意味がない」と思い込んでしまい、行動を起こせなくなります。
小さな失敗でも深く落ち込む
たとえば、仕事や家事でちょっとしたミスをしただけで、「やっぱり自分はダメだ」と自己否定に陥ることも。
選択に自信が持てない
自分で決めるのが怖くなり、「誰かに決めてもらいたい」と依存的になる傾向が出てきます。
2. 人間関係への影響
相手の顔色をうかがいすぎてしまう
自分より他人の評価を優先してしまい、「嫌われたくない」「迷惑をかけたくない」と考えて本音を言えなくなります。
頼まれごとを断れない
「断ったら嫌われるかも…」という不安から、無理なお願いも引き受けてしまい、ストレスがたまる一方に。
比較して劣等感を抱く
SNSなどで他人の成功を見て、「自分は何もできていない」と落ち込み、自信を失ってしまうことも。
3. 仕事・勉強への影響
自己評価が低く、挑戦を避けるようになる
「昇進しても自分には荷が重い」と思ってチャンスを逃したり、「失敗したら迷惑をかける」とリスクを避けすぎてしまいます。
成果が出ても素直に受け取れない
褒められても「たまたまです」と否定したり、「自分なんかが評価されるのはおかしい」と感じてしまう。
燃え尽き症候群になりやすい
完璧主義になりすぎて頑張りすぎ、心身が疲れてしまい、やる気が出なくなることも。
ネガティブな思考の悪循環とは?
自己肯定感が低い状態では、以下のような悪循環に陥りやすくなります。
- 落ち込む
- 自分を責める
- 行動できなくなる
- さらに自信をなくす
- また自分を責める……
このようなループは、意識しないと抜け出すのが難しいのが特徴です。
自己肯定感は「変えられる」
ですが、安心してください。
自己肯定感は、生まれつきのものではなく、後から育てることができます。
少しずつ考え方や行動の習慣を変えていけば、確実に自己肯定感は高まっていきます。
次の章では、具体的にどうすれば自己肯定感を高められるのか、
7つの実践的な方法を詳しく紹介していきます。
自己肯定感を高める7つの方法
「自己肯定感が低い」と感じている人の多くが、「自分にはどうしようもない」と思いがちです。
でも実は、日々のちょっとした考え方や行動を変えることで、自己肯定感は少しずつ高めていくことができます。
ここでは、心理学や実践事例をもとにした、7つの方法を紹介します。
方法①|小さな成功体験を積み重ねる
成功体験は、自信の「貯金」です。
大きな成果ではなく、「できたこと」に目を向けてみましょう。
- 朝ちゃんと起きられた
- 10分だけでも机に向かえた
- メールを1件返信した
こうした小さな達成感を毎日重ねていくことで、
「自分って、やればできるかも」という感覚が育っていきます。
もし、どんなことを書いたらいいの?と悩んでいる人は、この記事も参考にしてみてください!
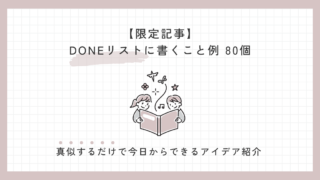
方法②|比較を手放す
自己肯定感を下げる最大の敵は、「他人との比較」です。
SNSを見て、「あの人はすごいな」と思うのは自然なことですが、
他人の“結果”と自分の“過程”を比べても意味がありません。
- 比較対象は「昨日の自分」にする
- SNSを見る時間を意識的に減らす
- 他人の成功は「刺激」として見るように意識する
方法③|自分の感情に寄り添う
「自己肯定感」は、「自分に優しくすること」から始まります。
自己肯定感と関連してよく出てくる「セルフコンパッション」とは、自分の失敗や弱さを責めずに受け入れる力のことを言います。
- つい落ち込んでしまったときに、「そういう日もあるよね」と自分に声をかける
- 自分が親友だったら、どう声をかけてあげるか?を考える
方法④|「できたこと」に注目する習慣をつける
人はつい、「できなかったこと」ばかりに目が向きがちです。
それでは自己肯定感は育ちません。
まずは自己肯定感を育てるために、ポジティブなことに意識を向ける習慣を作りましょう。
- 1日3つ「できたこと」をノートに書く(いわゆる「できたこと日記」)
- 朝や夜のルーティンの中に取り入れると習慣化しやすい
私も実際に夜寝る前によかったことを3つ書く習慣を続けています。
寝る前にポジティブなことに目を向けられるため、いい気持ちで寝ることができるのでおすすめです!
方法⑤|健康的な生活リズムを整える
実は、心の状態と体の状態は密接に関係しています。
自己肯定感が低くなる原因の1つが、「疲れ」です。
体のためだけでなく、心を労るためにも、健康的な生活リズムを心がけましょう。
特別なことはしなくても大丈夫です。
例えば、たった5分の散歩でも、脳内ホルモン(セロトニン)の分泌が活性化され、ポジティブな気分になります。
方法⑥|他人からの評価を減らす
「他人の目」を気にしすぎると、自分を見失いやすくなります。
大事なのは、「自分がどう思うか」です。
- 「自分はこれをやって楽しかった?」
- 「この選択に、自分らしさがあった?」
- 「自分は、どうしたかったの?」
- 「これをやっている自分のことは好き?」
行動や判断に迷ったとき、「この行動をした自分のことを好きになれるか?」で判断をすると、どんどん自分ベースで考えられるようになります。
少しずつでも、自分の価値観に軸足を戻していくために、積極的に自分への問いかけを行なっていきましょう。
方法⑦|自分を認めてくれる人とつながる
自己肯定感は、自分だけで育てるのが難しいときもあります。
そんなときは、あなたの価値を認めてくれる人の言葉や存在が支えになります。
- 安心して話せる友人・家族に相談する
- 「話すだけでもいい」と思って声をかけてみる
- 同じような悩みを持つ人と共感できる場(オンラインコミュニティなど)を見つける
逆に、あなたのやりたいことや行動を否定してくる人は、あなた自身のことを大切にしてくれない存在である可能性が高いです。
そんな人とは程よく距離を取ることも一つの選択です。
自分のことを大切にしてくれる人と繋がることで、自己肯定感はぐんぐん育っていきます。
今日からできることから、少しずつ
どれも一気にやろうとせず、「まずは1つだけやってみる」ことが大切です。
自己肯定感は、一夜にして高まるものではありません。
だけど、少しずつ積み重ねることで、確実に「自分を信じる力」は育っていきます。
自己肯定感と自己効力感の違い
「自己肯定感」と似た言葉に、自己効力感(じここうりょくかん)というものがあります。
どちらも「自分に対する信頼」に関係していますが、意味合いは少し異なります。
この章では、それぞれの違いを明確にしながら、どう活かしていけばよいかをお伝えします。
自己肯定感とは?
前章でもお伝えしたとおり、自己肯定感とは、ありのままの自分を受け入れ、価値ある存在として認める感覚です。
- 成功・失敗に関わらず、自分に価値を見出す
- 自分の存在そのものに「OK」を出す感覚
- 「自分はダメじゃない」と思える土台のようなもの
たとえば、仕事で失敗しても「うまくいかなかったけど、自分には価値がある」と思える状態が、自己肯定感がある人です。
自己効力感とは?
一方で、自己効力感とは、「自分には、特定の行動や課題をやり遂げる力がある」という確信のことを指します。
これは、アメリカの心理学者アルバート・バンデューラによって提唱された概念で、英語では self-efficacy(セルフ・エフィカシー) といいます。
- 具体的な行動への自信(例:プレゼンを成功させる、試験に合格する)
- 「自分ならできる」と思える心理的な力
- 過去の成功体験や周囲のサポートで高まる
違いを図でイメージすると…
| 自己肯定感 | 自己効力感 | |
|---|---|---|
| 意味 | 自分の存在を肯定する感覚 | 行動を成功させる自信 |
| 影響するもの | 感情、人格、人間関係 | パフォーマンス、やる気 |
| 高め方 | 自分を責めない・受け入れる | 成功体験・練習・目標設定 |
| 例 | 「失敗しても私は大丈夫」 | 「これは自分にできる」 |
このように、似た言葉ですが、意味や影響するものには違いがあります。
自己肯定感と自己効力感はどちらも大切。でも順番がある
多くの人が「やる気が出ない」「行動に自信がない」と感じたときに、
自己効力感だけを高めようとしてしまいます。
しかし、自己効力感の土台には自己肯定感が必要です。
そのため、正しくどちらも身につけるためには、
- 自己肯定感:どんな自分もOKと思える土台
- 自己効力感:その上に積み上げていく行動の自信
という順番で育てていくのが理想です。
両方をバランスよく育てるには?
- まずは「できない自分」にもOKを出す(自己肯定感)
- そのうえで、小さな成功体験を積み重ねる(自己効力感)
たとえば、「勉強が苦手な自分も、それはそれでいい」と受け入れたうえで、
「まずは10分だけ机に向かってみよう」と実践する。
このプロセスが、自己肯定感と自己効力感の両方を高める第一歩になります。
次の章では、こうした感覚を習慣として定着させるコツについて紹介していきます。
「わかる」から「できる」へ。日々の生活に取り入れる方法をお伝えします。
自己肯定感を高める習慣を身につけるには?
自己肯定感を高めるためには、知識や気づきだけでなく、「習慣化」がとても大切です。
どんなに素晴らしいことでも、1回だけやって終わってしまえば、自己肯定感はなかなか定着しません。
では、どうすれば無理なく続けられるのか?
ここでは、心理学や行動科学の視点も交えながら、習慣化のポイントを紹介します。
習慣化のコツ①|ハードルを下げる
自己肯定感を高める行動は、「特別なこと」ではなく「日常の中に溶け込ませる」のがカギです。
- 最初は「1日1分」でOK
- すぐにできることから始める(例:深呼吸する・ありがとうを言う)
- 「完璧主義」は習慣の敵!
たとえば、「毎日ノートに感情を書き出す」という習慣を作りたい場合、
「まずは1行だけ書く」と決めて始めると継続しやすくなります。
習慣化のコツ②|きっかけ(トリガー)を決める
行動を習慣化するには、「いつやるか」を明確にすると継続率が上がります。
これは「If-Thenプランニング(もし~なら、~する)」という行動科学の手法です。
- 「歯を磨いたら、そのあとで1分間深呼吸する」
- 「朝起きたら、できたことを1つノートに書く」
- 「夜ベッドに入る前に、自分に『今日もおつかれさま』と言う」
こうした日常動作にセットでくっつけることで、意識せずとも続けやすくなります。
習慣化のコツ③|「できた記録」を残すことでモチベーション維持
自分の行動を目に見える形で残すことで、達成感や成長実感を得やすくなります。
- チェックリストに毎日◯をつける
- アプリで習慣トラッカーを使う(例:Habitify、Streaks など)
- 手帳やノートに簡単なメモを書く
こうすることで、自分を褒めるチャンスが増え、自己肯定感も自然と育ちます。
習慣化のコツ④|自分に合ったスタイルを見つける
自己肯定感の高め方には、「これが正解」というものはありません。
大切なのは、あなたが「これなら続けられる」と思える方法を選ぶことです。
- 書くのが好きな人 → 日記・ノート習慣
- 話すのが好きな人 → 誰かに話す習慣
- 動きながら考えたい人 → 散歩しながら自分と対話する
やり方にこだわらず、「自分に合っているかどうか」で決めましょう。
習慣化のコツ⑤|うまくいかなくても、自分を責めない
習慣化に失敗する日があっても、それは「よくあること」です。
「また明日からやればいい」と思えること自体が、自己肯定感を育てる行動になります。
習慣は「積み重ねた分」だけ自信になる
小さな習慣の積み重ねは、やがて「自分はちゃんと続けられる」という確かな自己信頼につながります。
そしてそれは、自己肯定感の大きな柱となっていきます。
いきなり大きく変わろうとするのではなく、まずは自分にできる範囲のことからコツコツやっていきましょう。
自己肯定感を高めたい人におすすめの本3選
「もっと深く学びたい」「継続的に取り組んでいきたい」と思ったときに頼りになるのが本です。
ここでは、自己肯定感を高めるのに役立つ、初心者にもおすすめの実践的な3冊を紹介します。
どれも読みやすく、日常の中に取り入れやすい工夫がされています。
おすすめの本①|『自己肯定感ノート』中島輝 著
臨床心理カウンセラーであり、自身も自己肯定感の低さに悩んだ経験を持つ中島輝さんによる一冊。
この本では、自己肯定感とはなんなのか、どうやって育てていくといいのかが詳しく書いてあります。本の中で紹介してあるワークはどれも実践しやすいため、初めての方でも取り入れやすい内容になっています。
🔍 こんな人におすすめ
- 思考を整理するのが苦手な人
- すぐに実践できる方法を探している人
- 自分に自信を持ちたいけど、何から始めればいいかわからない人
おすすめの本②|『うまくいっている人の考え方』ジェリー・ミンチントン 著
世界でシリーズ累計300万部超のベストセラー。
自己肯定感を高めるためのシンプルな「考え方のコツ」100個がまとめられており、どこから読んでもOKな構成になっています。
一章が短いため、隙間時間にも読むことができます。
🔍 こんな人におすすめ:
- 忙しくて長い本は読めない人
- 気がつくと自分を否定してしまう人
- 気持ちを切り替える「ヒント」が欲しい人
3. 『嫌われる勇気』岸見一郎・古賀史健 著
アドラー心理学をベースにした哲学的対話形式の本。
「人は変われる」という力強いメッセージが込められており、自己肯定感の根本的な考え方を見直すことができる一冊です。
🔍 こんな人におすすめ:
- 自己肯定感の「正体」を深く理解したい人
- 考え方そのものを変えていきたい人
- 自分の人生を「自分で選ぶ」という覚悟を持ちたい人
どの本も「読むだけで終わらせない」のがカギ
どの本も素晴らしい内容ですが、もっとも大切なのは、
「読んで、感じて、少しでも行動に移すこと」です。
たとえ1つの言葉でも、自分の心に響いたら、ぜひメモしたり、声に出してみたりしてください。
その小さな行動が、自己肯定感を育てる一歩になります。
今日から始める第一歩
あなたにおすすめしたいのは、「1日1つ、自分を認める言葉をつぶやくこと」です。
たとえば…
- 「今日はちゃんと起きられた、えらい!」
- 「疲れてるのに頑張ってる、自分すごい」
- 「うまくいかなかったけど、チャレンジできた」
こういった“小さな自己承認”を、毎日の習慣にしてみてください。
それが、自己肯定感という大きな木の根っこを育てていきます。
おわりに
自己肯定感は、持っている人が特別なのではなく、誰でも育てることができるものです。
焦らず、比べず、少しずつ。
このブログが、あなたの「自分を好きになる旅」の一歩になれば嬉しいです。



